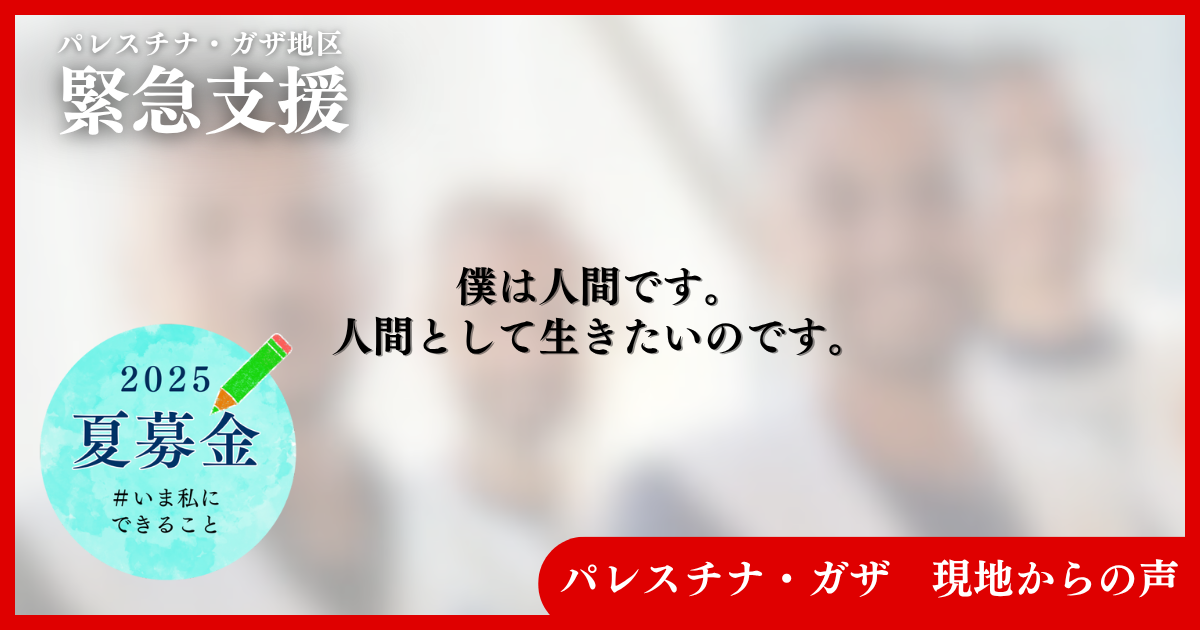活動の現場からREPORT

ガザ2年
2023年10月7日、ガザ側からの奇襲攻撃に対する「報復」として始まったイスラエル軍によるガザ攻撃。容赦なく続く前代未聞の規模の侵攻を、2年もの間、私たちは目撃し続けています。
2025年10月5日現在、報告されているだけで死者は6万7千人を超え、そのうち1.85万人は子ども、1万人は女性です。また、17万人が重軽傷を負い、そのうち4.2万人は四肢の切断や重度の熱傷など、今後の人生に大きく影響する重傷を負っています。
人々は2年もの間、何度も何度も強制的に避難をさせられました。燃料不足により交通機関は2年前とは比較にならないほど高額で、多くの人は破壊され砂利道になった道路を歩いて逃げるしかありません。持てるだけの荷物を持って、歩けない家族を肩に担いだり、壊れた車いすを使って何キロも徒歩で避難しなければならないのです。
ガザへの食料を含む支援物資の搬入もイスラエル軍によって厳しく制限され続け、今年8月、ついに国連は正式にガザで飢きん(IPCフェーズ5)が起きていることを発表しました。(※1)
人々は想像を絶する状況の中、恐怖や不安、空腹、心身の痛みに苛まれ、苦しみ続けています。
「日本は遠いから」「関係ないから」という声が聞かれることもありますが、日本もこのような状況を許してきた国際社会の一員です。これまで、JVCは現地で活動するNGOの一つとして、他団体と共に日本政府への働きかけを続けて来ました。
また、去る10月4日には、昨年に引き続きパレスチナで支援活動を行う日本のNGOが中心となり、報告会とキャンドルアクションのイベント「停戦を、食料を、今すぐに」を実施しました。

10月4日に行われたイベント「停戦を、食料を、今すぐに」の様子
各団体から、それぞれの活動や現場からの声が共有され、亡くなったすべての方々の追悼と平和への願いを込めて1分間の黙祷が行われました。会場には250名ほどが参加し、キャンドルを灯し共にガザへの祈りを捧げました。
一刻も早く恒久的な停戦が実現し、人々が普通の暮らしを取り戻せるよう、JVCは他団体などと協力しながら日本政府への働きかけを継続すると共に、現地の人々に支援を届け続けます。
JVCガザ現地スタッフからのメッセージ
この2年間で、ガザの「顔」とそこに息づく生活のリズムは、一変してしまいました。
終わることのない苦しみ、数え切れないほどの喪失。包囲、破壊、そして生活に最も必要な物さえも欠乏する中を、ただ生き抜こうとする日々。
しかし、こうした状況下でも、私たちは心の内に、人類の力、人間性への深い信頼を抱き続けています。世界の良心が一つに結集すれば、苦しみを止め、再び希望を取り戻すことができると信じています。
ガザから、私たちは日本の皆さんに語りかけます。
皆さんは、困難な時に常にパレスチナの人々に寄り添い、思いやりと支援の手を差し伸べることで、家族の苦しみを和らげ、尊厳と希望の精神を支えてきました。
戦争と破壊の悲劇を自ら経験した日本の皆さんは、安全を失うことの意味を理解し、灰の中から再び立ち上がる平和を真に尊ぶことを、私たちは知っています。
今日、ガザは世界で最も深刻な人道危機の一つに直面しています。
200万人以上の人々が、電気もきれいな水もなく、子どもたちのための十分な医薬品や食料もなく、耐え難い状況の中で暮らしています。何千もの家屋が破壊され、病院は本来のキャパシティをはるかに下回る状態で稼働し、人々は枕の上ではなくテントの下で、尊厳と希望を奪われ、恐怖の中で眠りについています。
このような痛ましい現実の中にあっても、「市民の命を守る」という人道上の責務は変わりません。
私たちは毎日、現場で、自身も空腹でありながら子どもに食べさせようとする母親、休むことなく精力的に働く医師、そして次にどこへ向かうべきか分からず食料の箱を運ぶ若者の姿を目にしています。
今、これまでよりもいっそう切実に、私たちは停戦、そして平和を必要としています。
今日、私たちが日本の皆さんに伝えたいのは、悲しみだけではなく、私たちが共有する希望――国境を超え得る人間性への希望のメッセージです。
皆さんの声によって平和と正義が訴え続けられ、ガザとの連帯が続くことを切に願います。世界がそうした良心を必要としているように、ガザは世界を、皆さんを必要としているからです。
瓦礫と塵の下から、私たちは今もなお、ただ平和に暮らすことを願う子どもたちの声に、世界が耳を傾けることを夢見ています。
ガザから、日本の皆さんへ、愛と深い感謝を込めて。
平和は遠い願いではなく、私たちが守らなければならない人類の約束であることを、私たちは共に、信じましょう。
※1:飢きんとは、極度の食料不足や急性栄養不良、そして餓死が大規模に発生する「壊滅的な飢餓(IPCフェーズ5)」と呼ばれる状態を指します。IPC(総合的食料安全保障レベル分類)の栄養状況の判断は、国連の複数の機関、援助機関、そして技術的な専門家が協力し、データ分析に基づいて、技術的な分類手法を用いて食料安全保障レベルを5段階で評価するものです。