イベントに参加するEVENT

JVCのイベント
JVCでは、年間を通して様々なイベントを企画・実行しています。
硬くまじめなものから楽しく気軽に参加できるものまで、活動幅広さ同様の多彩さです。
ぜひ一度ご参加ください。
- オンライン
 開催予定2025年8月2日(土)
開催予定2025年8月2日(土)8/2(土)【夏休み特別企画】家族で考える「壁で分断された国パレスチナ」ピーススタディツアー
- オンライン 対面
 開催予定2025年7月13日(日)13:00~15:00
開催予定2025年7月13日(日)13:00~15:007/13(日)対面&オンライン【なぜ私たちは済州島へ】2025 次世代のための済州4・3 ピースツアー 報告会 @東京
- 対面
 開催予定2025年7月6日(木)13:30~16:30
開催予定2025年7月6日(木)13:30~16:307/6(日)パレスチナのことを知ろう 映画上映会&トークイベント@山梨
- 月刊JVC
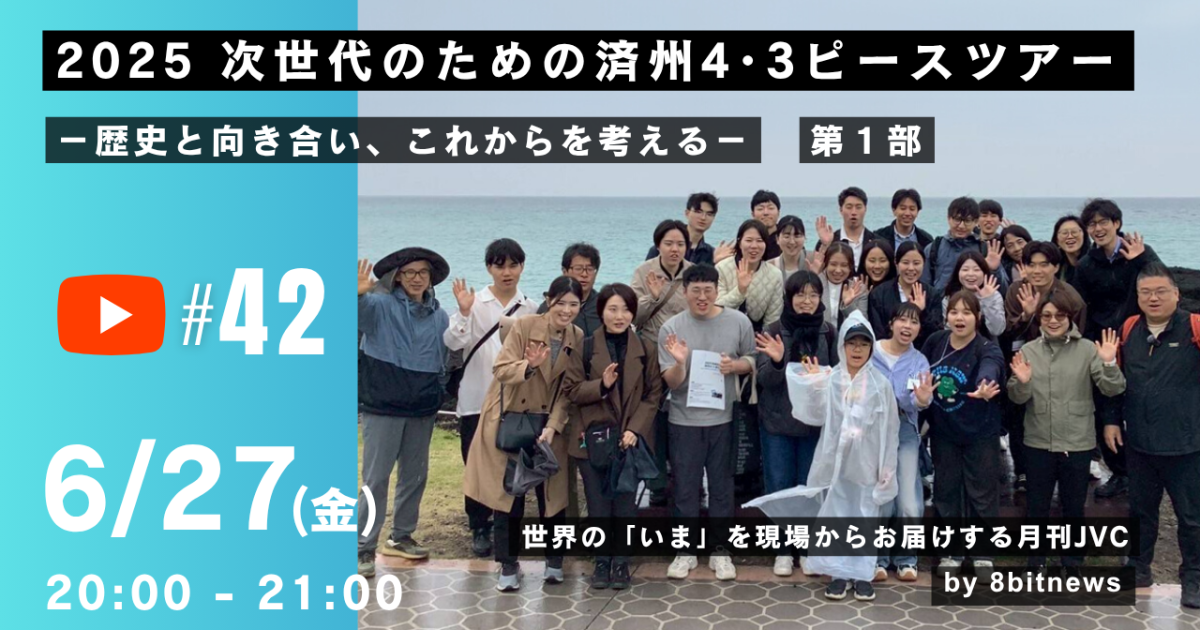 開催予定2025年6月27日(金)20時~、6月28日(土)20時~
開催予定2025年6月27日(金)20時~、6月28日(土)20時~6/27~6/28【月刊JVC#42】2025次世代のための 済州4・3ピースツアー ~歴史と向き合い、これからを考える~
- 対面
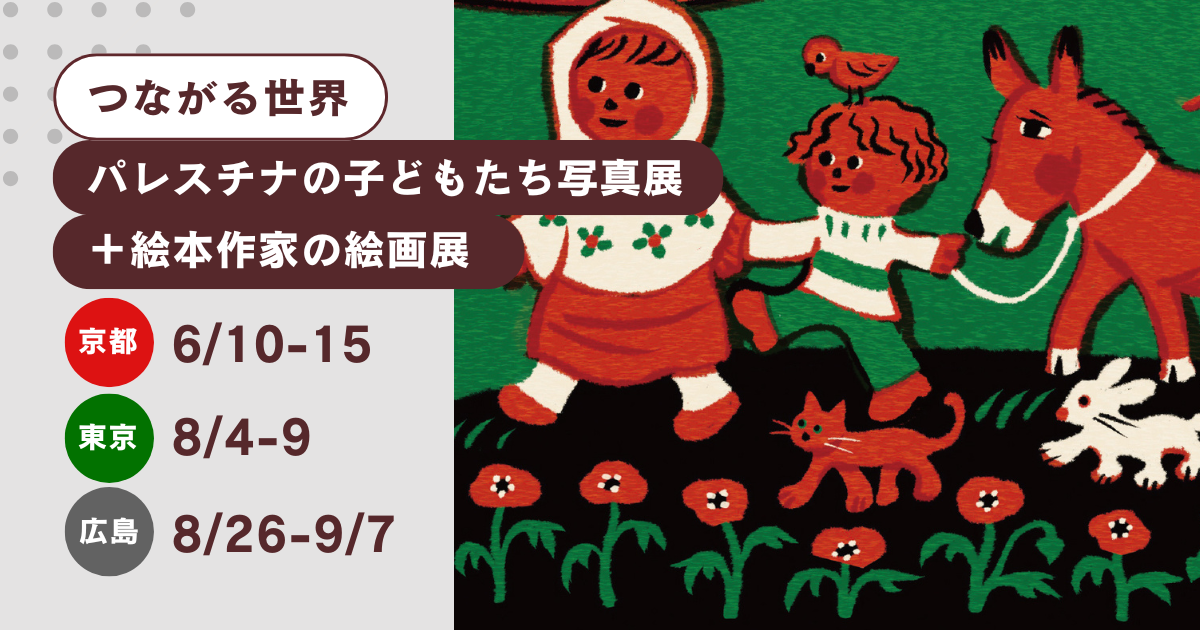 開催予定2025年6月10日(火)~
開催予定2025年6月10日(火)~【6/10より開催】つながる世界〜パレスチナのこどもたち写真展+絵本作家の絵画展
- 対面 オンライン
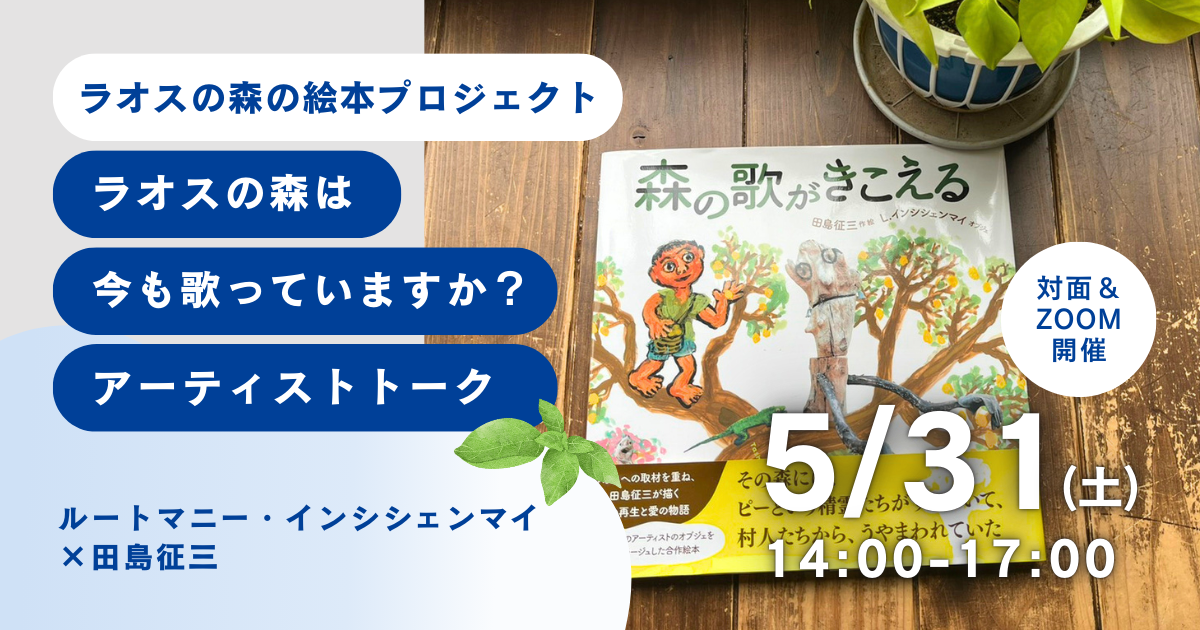 終了2025年5月31日(土)
終了2025年5月31日(土)5/31開催【田島征三氏登壇】ラオスの森は今も歌っていますか?アーティストトーク
- 対面 オンライン
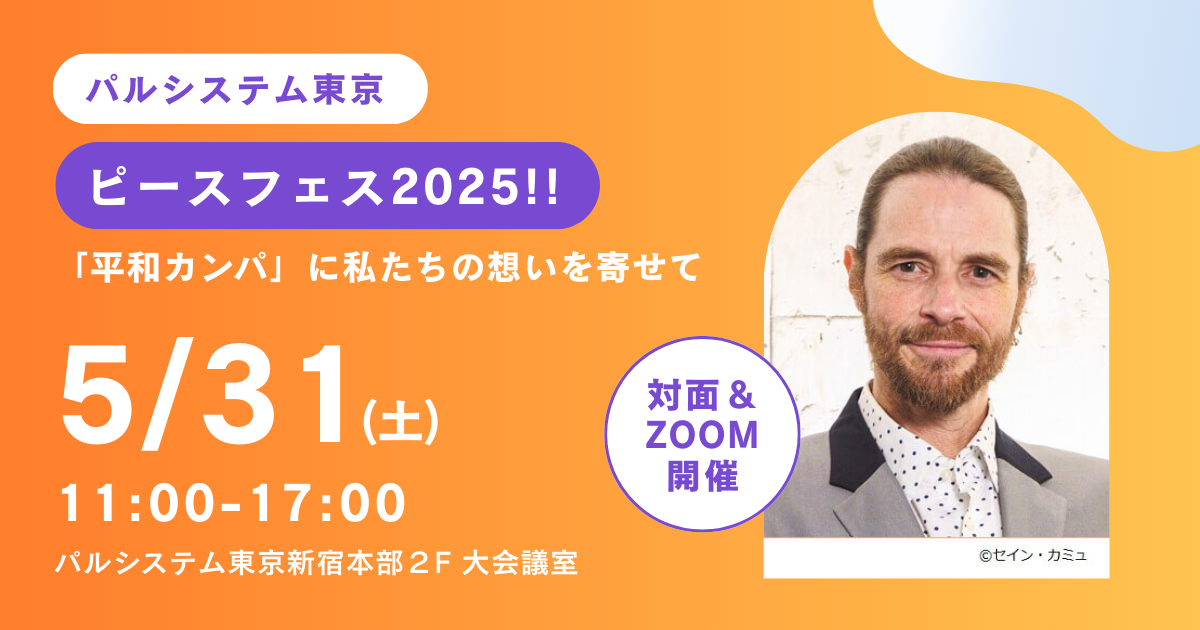 終了2025年5月31日(土)11:00-17:00
終了2025年5月31日(土)11:00-17:005/31(土) 【パルシステム東京】ピースフェス2025‼ ~「平和カンパ」に私たちの想いを寄せて~
- 対面
 終了2025年5月3日(土)
終了2025年5月3日(土)5/3(土)2025憲法大集会に登壇します
- 対面
 終了2025年4月30日(水)19:00-20:30
終了2025年4月30日(水)19:00-20:304/30(水)【緊急セミナー】「ミャンマー中部大地震 人びとに届く支援とは」
- 対面
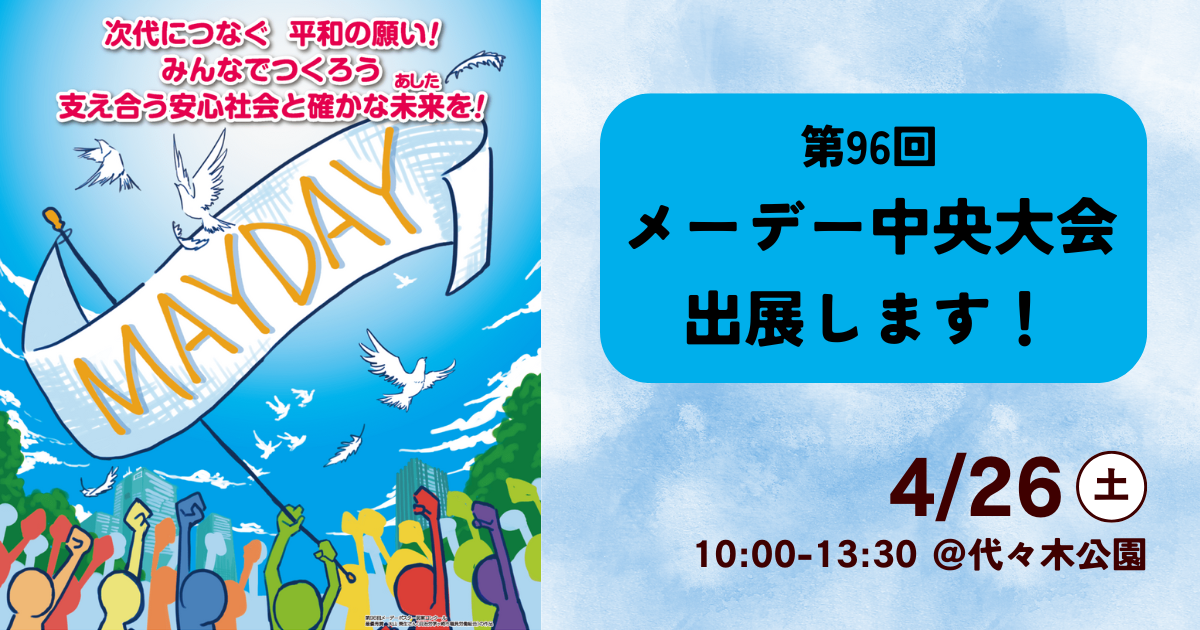 終了2025年4月26日(土)10:00~
終了2025年4月26日(土)10:00~4/26(土)第96回メーデー中央大会に出展します!
- オンライン
 開催予定2025年8月2日(土)
開催予定2025年8月2日(土)8/2(土)【夏休み特別企画】家族で考える「壁で分断された国パレスチナ」ピーススタディツアー
- オンライン 対面
 開催予定2025年7月13日(日)13:00~15:00
開催予定2025年7月13日(日)13:00~15:007/13(日)対面&オンライン【なぜ私たちは済州島へ】2025 次世代のための済州4・3 ピースツアー 報告会 @東京
- 対面
 開催予定2025年7月6日(木)13:30~16:30
開催予定2025年7月6日(木)13:30~16:307/6(日)パレスチナのことを知ろう 映画上映会&トークイベント@山梨
- 月刊JVC
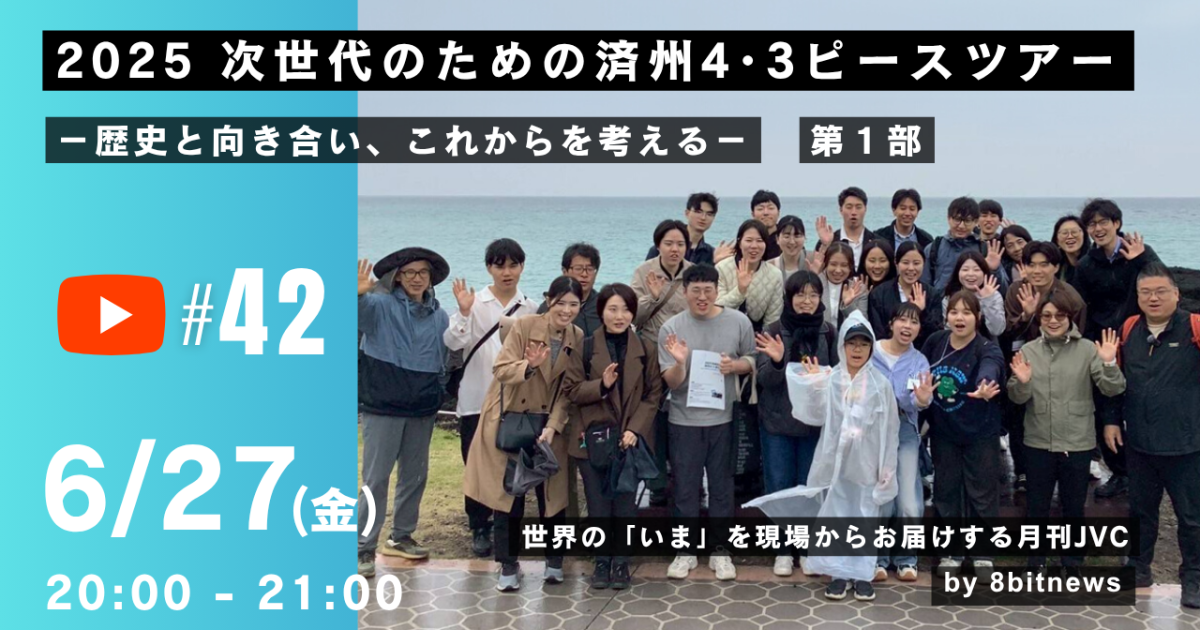 開催予定2025年6月27日(金)20時~、6月28日(土)20時~
開催予定2025年6月27日(金)20時~、6月28日(土)20時~6/27~6/28【月刊JVC#42】2025次世代のための 済州4・3ピースツアー ~歴史と向き合い、これからを考える~
- 対面
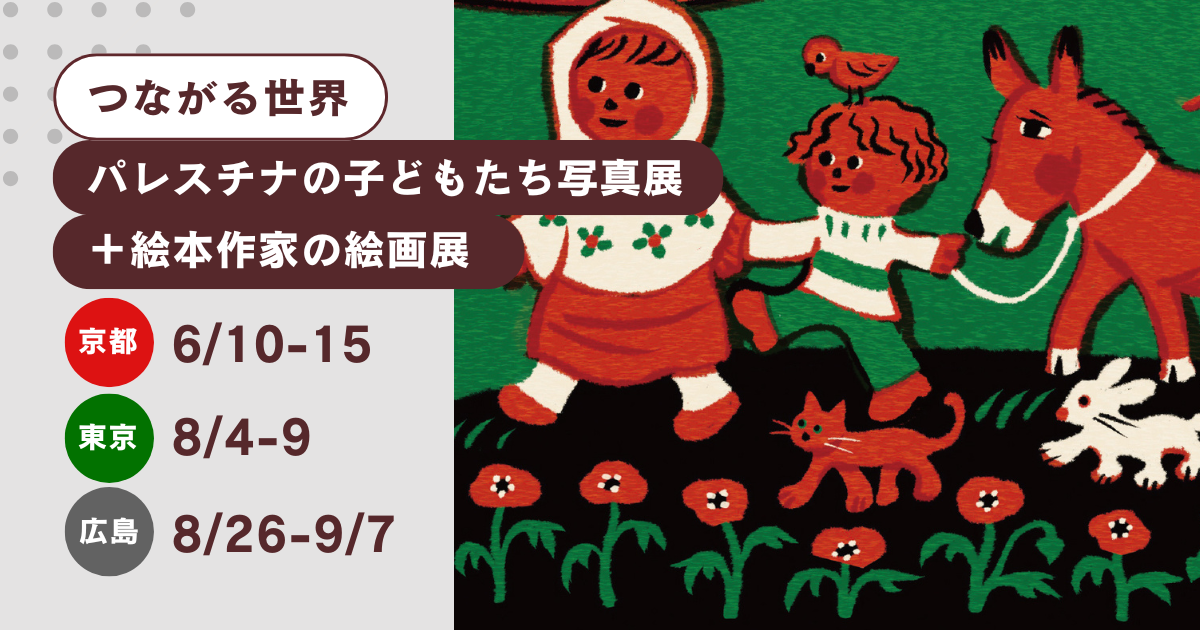 開催予定2025年6月10日(火)~
開催予定2025年6月10日(火)~【6/10より開催】つながる世界〜パレスチナのこどもたち写真展+絵本作家の絵画展
- 対面 オンライン
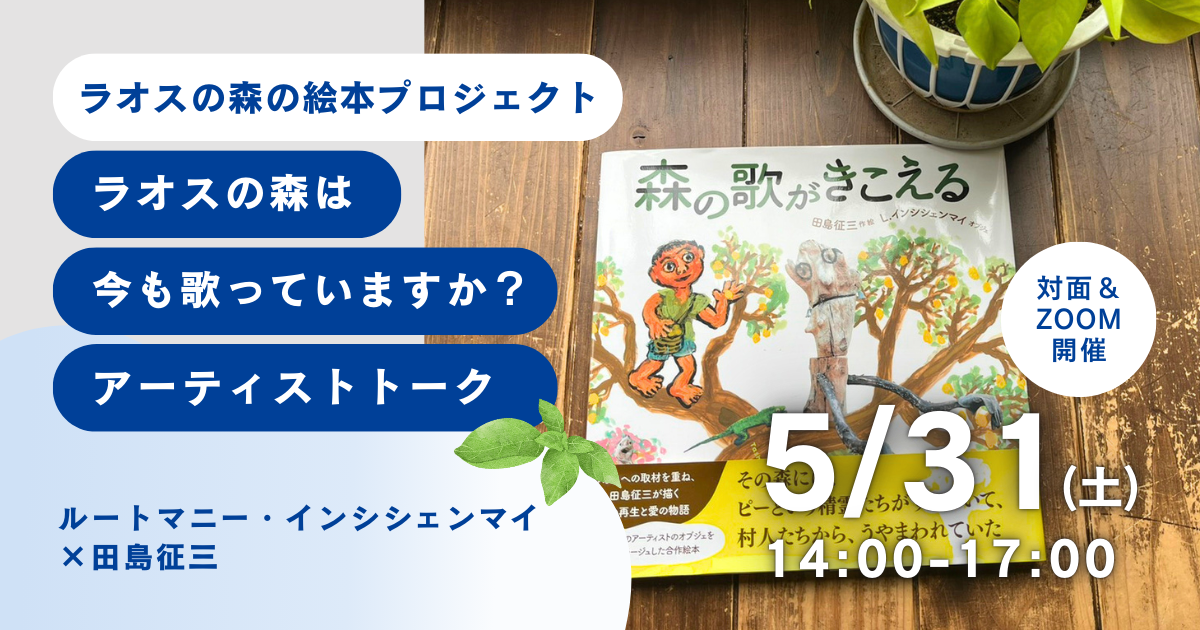 終了2025年5月31日(土)
終了2025年5月31日(土)5/31開催【田島征三氏登壇】ラオスの森は今も歌っていますか?アーティストトーク
- 対面 オンライン
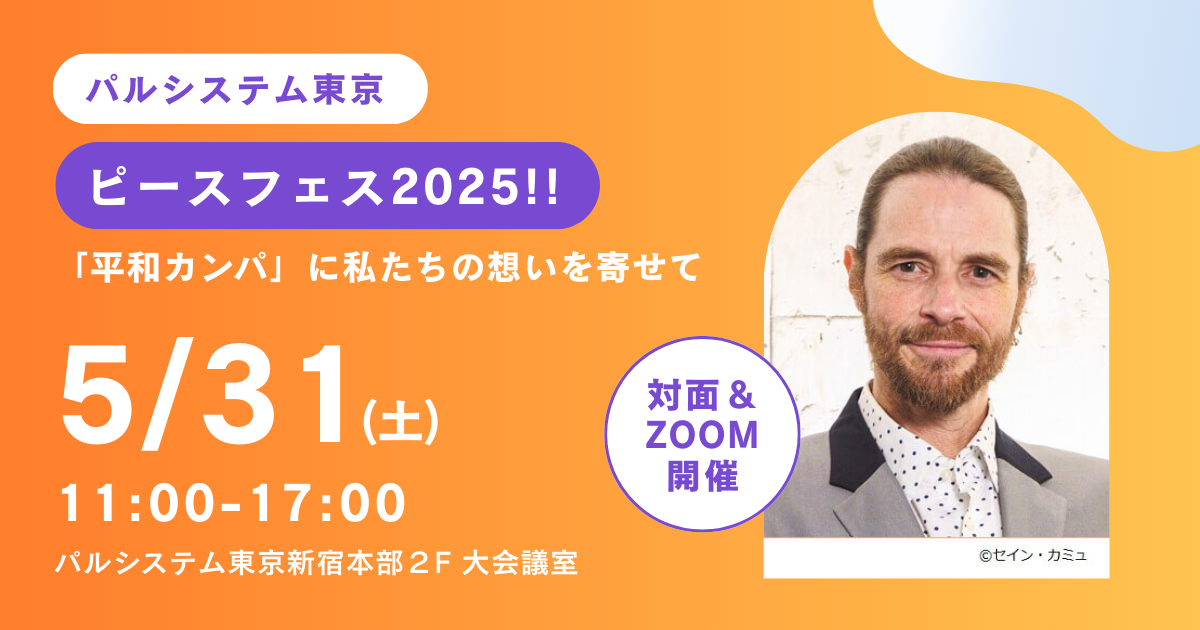 終了2025年5月31日(土)11:00-17:00
終了2025年5月31日(土)11:00-17:005/31(土) 【パルシステム東京】ピースフェス2025‼ ~「平和カンパ」に私たちの想いを寄せて~
- 対面
 終了2025年5月3日(土)
終了2025年5月3日(土)5/3(土)2025憲法大集会に登壇します
- 対面
 終了2025年4月30日(水)19:00-20:30
終了2025年4月30日(水)19:00-20:304/30(水)【緊急セミナー】「ミャンマー中部大地震 人びとに届く支援とは」
- 対面
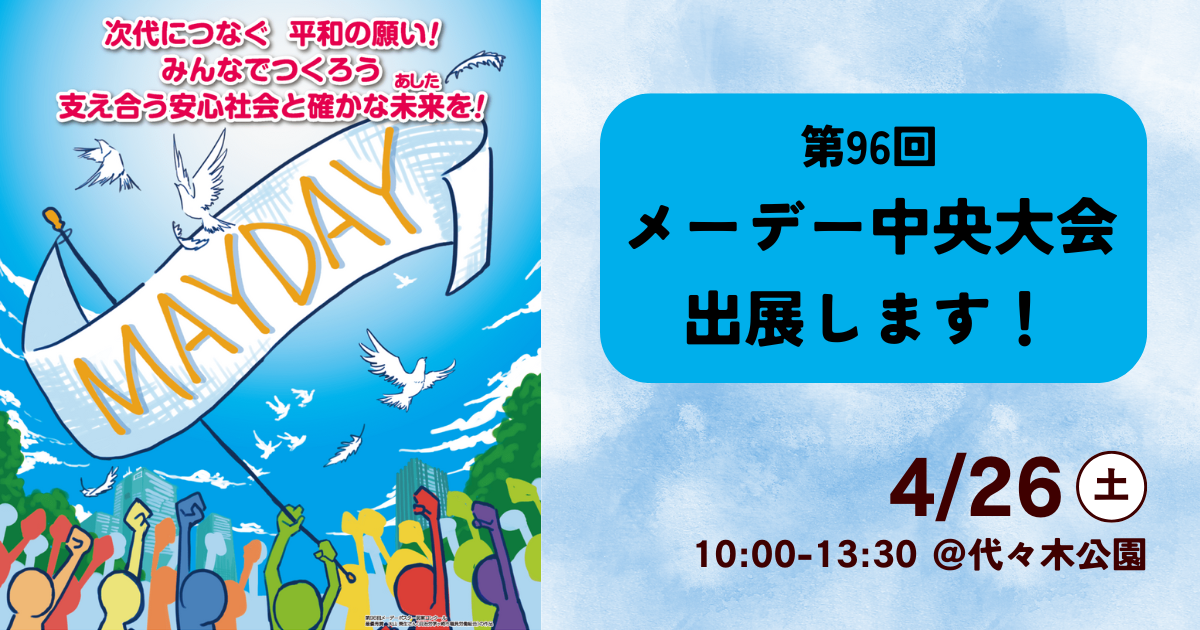 終了2025年4月26日(土)10:00~
終了2025年4月26日(土)10:00~4/26(土)第96回メーデー中央大会に出展します!
- 対面
 終了2025年4月13日(日)14:00~15:30
終了2025年4月13日(日)14:00~15:304/13(日)開催【戦闘から2年スーダンに注目して!】NGO共同記者会見&バナーアクション
- オンライン
 終了2025年3月29日 (土)19:00~21:00
終了2025年3月29日 (土)19:00~21:003/29(土)【春休み特別企画】壁で分断された国パレスチナ ピーススタディツアー 100年後も変わらない学びを ~パレスチナが問いかける「平和」と「未来」~
- 対面
 終了2025年3月28日(金)
終了2025年3月28日(金)3/28(金)対面開催【インターン企画】「国際協力って何だろう?」ーNGOの人と話してみよう!ー
- 月刊JVC
 終了2025年3月19日(水) 21:00-22:00
終了2025年3月19日(水) 21:00-22:003/19(水)【月刊JVC#41】占領下のエルサレムー「聖都」はどうなるのかー
- 対面
 終了2025年3月8日(土)13:30~15:00
終了2025年3月8日(土)13:30~15:003/8 対面開催【国際女性デー講演会】占領・紛争下に生きるパレスチナの女性たち
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 2025年06月 | 2025年08月 » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
期間で絞り込む
- 2014年10月(1)
- 2022年09月(1)
- 2022年10月(7)
- 2022年11月(3)
- 2022年12月(4)
- 2023年01月(2)
- 2023年02月(6)
- 2023年03月(4)
- 2023年04月(2)
- 2023年05月(4)
- 2023年06月(6)
- 2023年07月(10)
- 2023年08月(7)
- 2023年09月(6)
- 2023年10月(7)
- 2023年11月(16)
- 2023年12月(7)
- 2024年01月(4)
- 2024年02月(2)
- 2024年03月(7)
- 2024年04月(3)
- 2024年05月(4)
- 2024年06月(5)
- 2024年07月(8)
- 2024年08月(6)
- 2024年09月(8)
- 2024年10月(4)
- 2024年11月(4)
- 2024年12月(5)
- 2025年01月(3)
- 2025年02月(5)
- 2025年03月(6)
- 2025年04月(3)
- 2025年05月(3)
- 2025年06月(2)
- 2025年07月(2)
- 2025年08月(1)














