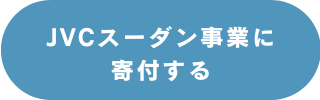活動の現場からREPORT

はじめてのスーダン(2)~内部監査とポートスーダンでの活動~
 (5).png)
こんにちは、東京事務所で総務・労務・海外事業サポートを担当している木村万里子です。2025年8月中旬に10日間ほど内部監査のためにスーダン事務所のあるポートスーダンを訪問しました。今回は、内部監査の様子をお伝えします。
【レポート第1弾】「はじめてのスーダン(1)~ポートスーダンを歩く~」はこちら!
内部監査とは…?
今回のスーダン出張の主目的は内部監査でした。「内部監査」というと会計検査院の立ち入り調査的な物々しさを思い浮かべる人もいるかもしれませんが、私たちはみなさまの貴重なご寄付をいただいて活動を実施していることもあり、内部の第三者が定期的に活動や会計管理の実態を客観的に確認する「内部監査」という作業は、活動の透明性を確保するため、関係者への説明責任としても欠かせません。JVCでは東京事務所では毎年、海外事務所では2~3年に一度現地での内部監査を実施しています。
内部監査の主な項目は3つ。1つ目は事務所運営、2つ目は会計管理、3つ目は事業管理です。出張前に作成したチェックリストに従い、現地で管理している書類を見ながら、スタッフへのヒアリングを通じて、決められたルールに従い管理できているか、計画された内容で活動が実行されているかなどひとつひとつ確認していきました。前回(2022年)の時はカドグリ事務所での監査も実施したのですが、今回は治安状況の関係でポートスーダン事務所のみの実施となりました。

現地パートナー団体のスタッフ(右)にもヒアリング
現地で活躍するスタッフたち
改めて、今中と現地副代表モナから2023年4月のスーダン内戦発生時以降、現在に至るまでの過程を聞きましたが、ポートスーダンに移動してからも、事務所探し、NGO登録の更新、ビザの手続き、銀行手続き、安全管理、ファンドの申請、各種報告書、現地からの発信などなど大変な状況のなかカドグリ事務所や東京事務所スタッフとともに、何とかこの難局を乗り越えてきた軌跡を確認することができました。
▼モナと今中が再会するまでのエピソードはこちらから
【スーダン】度重なる退避を越えて私がやるべきこと 前編
特に、「ロジ」と呼ばれる事務所・事業運営や活動に必要な下準備的な必要不可欠な要素、NGO登録や事務所探し、ビザ手配、銀行とのやりとりなどはスーダンに限らずJVCのいずれの事業地でもすんなりいかないことが多く、たくさんの労力と時間がかかります。そのうえ、スーダンは政府機関も内戦に伴いハルツームからポートスーダンへの移転を余儀なくされたこともあり、その体制の立て直しの過程で新しいルールの制定・改廃がひっきりなしに行われていくという流動的な状況が今も続いています。そんなときはいかに正確な情報を得て、適切に対応していくか、そのためには援助機関やローカルなどに信頼のできる友人などネットワークをもっていると心強いです。その点、アラビア語を理解しスーダン駐在7年目になる今中、博士号をもち周囲からも「ドクトーラ(アラビア語で女性の博士・医師)」と呼ばれて尊敬されているモナのネットワークに出張中も大いに助けられました。

現地で裨益者にインタビューを行う今中とモナ
新しいプロジェクトの視察
事業については、ポートスーダンのある紅海州で今年7月に開始したコミュニティ支援の活動(※)について、現地パートナー団体(Abuhadiaアブハディーア)への訪問と活動の視察、裨益者へのインタビューを行うことができました。ポートスーダンの中心地域にある事務所から車で30分ほどのところにあるホシリ地区が活動地なのですが、そこへの移動も事前にNGOを管理している機関からの許可が必要なため、出張前には訪問できるかどうか確定していなかったのですが、何とか滞在中に許可を得ることができ訪問がかないました。やはり、現地にいって実際に活動の様子を見ることは、書類で活動内容を確認するだけではわからない裨益者の反応や実際の活動の様子、現地パートナー団体とのコミュニケーションなどさまざまなことを把握するうえでは貴重な機会となりました。
(※)本活動は、UNDPとの連携により実施しています。
「日本政府とUNDP、スーダン紅海州における国内避難民および受け入れコミュニティの食料安全保障と収入向上を目的とした100万米ドルのプロジェクトを開始」
紅海州自体がもともと食料不足にあったなか、2023年以降に発生した国内避難民により食糧事情がさらに悪化しました。この食料不足と貧困の問題に取り組むために、この地域での重たる収入源である漁業と農業にフォーカスし、それぞれのグループに対して必要な資材の提供、生計向上のための研修を実施しています。また、コミュニティを支えるには女性たちの活躍が欠かせないことから、男性だけでなく、女性のコミュニティリーダーを養成するための研修も行っています。
詳しいプロジェクト内容についてはこちら
私が訪問したときはちょうど男性および女性向けのコミュニティリーダー養成研修を行っていたので、視察させていただきました。男女ともホシリ地区の中のさらに細分化された5つの地域から3名ずつ選出されたリーダー候補生です。
男性向けのコミュニティリーダー研修
男性は学校の校舎が研修場所となっていました。アブハディーアのスタッフ、アブターレブさんがファシリテーターとなり、地域の課題について参加者とともにディスカッションを行いました。
 (4)-1.png)
女性向けのコミュニティリーダー研修
男性と違い読み書きが不自由な女性たちも多いようで、模造紙などは使わずファシリテーターが口頭で説明していました。女性はとくに家事や子育てで忙しいなか、時間と労力をつかってこの研修に参加した動機が知りたくて質問したところ、「コミュニティを良くしたいと思ったから、そのことに自身で学んだことを活かして貢献できることが嬉しい」という声がたくさん聞かれ、今後が楽しみになりました。
.jpg)
現地パートナー団体・アブハディーア
JVCは紅海州での活動経験はなかったので、現地パートナー団体との連携は欠かせません。アブハディーアは、紅海州を拠点としてコミュニティ開発を行う設立40年を迎える団体です。職員8名と大きな団体ではありませんが、地域の人たちとじっくり向き合って丁寧な活動を行っています。日本のNGOと働くのは初めてのようですが、私たちとの協働からも多くを学びたいと受け入れてくれました。余談ですが、お土産に「かすてら」と「かりんとう」をお渡ししたら、「かりんとう」が大好評でした。現地にも似たようなお菓子があるようです。

アブハディーアのスタッフと今中・モナ
10日間にわたる内部監査出張の後、監査内容を理事会やスタッフに報告して無事に任務が終了しました。しかしながら、細かい部分では改善の余地もあり、より良い活動のためにみんなで力をあわせて、これからも取り組んでいきたいと思っています。
※現在ポートスーダン市を含むスーダン全土は、外務省で危険度4(退避勧告)に指定されています。JVCでは安全管理体制を徹底し、セキュリティに関する特別な研修を受けたスタッフのみ駐在および出張を可能としています。また、常に現地の安全に関する情報を入手し分析、安全性を確認したうえで駐在・出張を行っています。本記事は現地の状況をお伝えするためのものであり、一般の方の渡航を促すものではないことはご理解ください。
執筆者プロフィール
.png)
群馬県出身。民間企業で働きながら国際協力NGOでボランティアを続けるうちにNGOの世界へ。イギリス大学院への留学後、複数のNGOに勤務。13年間で国内外あわせて16の緊急救援および教育支援、開発教育に携わる。支援活動で滞在した国は、中国雲南省、フィリピン、ラオス、カンボジア、バングラデシュ、ミャンマー、ネパール。2020年5月まではロヒンギャ難民支援に従事。これらの支援活動を通じ、より良い支援を行うためには自身も含め、支援する側の能力が重要であることを実感する。2020年12月~2024年7月までJVCエルサレム事務所駐在。2022年イエメン事業立上げに参画。令和6年度「信州大学同窓会連合会賞」受賞。