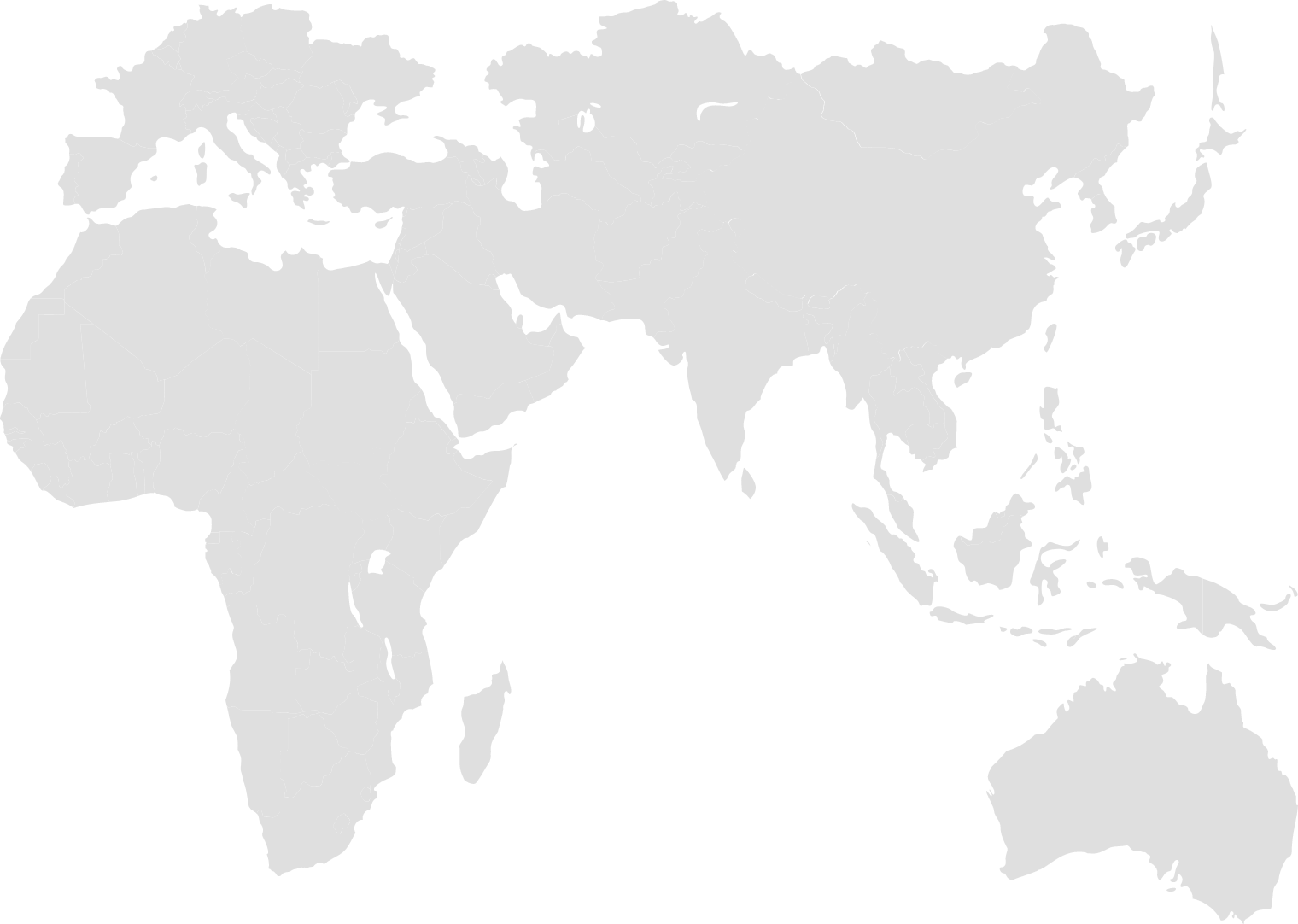JVCを知るABOUT

ビジョン・ミッション
JVCが
目指す社会
JVCの使命
グローバル化が進む今日の世界において、周縁化された人々の暮らしは、一層の差別、分断、抑圧といった構造的な暴力の中で困難な状況に直面しています。とりわけ市場競争の激化に伴う収奪的な開発、地域覇権を争う武力紛争は、現地の人々の命や自律的な日々の暮らしのための様々な権利を侵害しています。
JVCはこうした境遇に置かれた人々に寄り添い、みずから立ち上がろうとする人々と手を携え、社会変革の輪を広げていきます。
そのために、次の4つの具体的なミッション(使命)を掲げて活動します。
自然資源を保全し、
住民主権を尊重します。
収奪的な開発に対して、地域の資源を守り活用する実践や、声を上げ、あるいは問題意識を持つ当事者の取り組みを支えます。さらに、開発の実施主体や国際社会に対して問題点を指摘しその改善に向けた働きかけや政策提言を進めます。
公正な社会を実現し、
人々の権利を回復します。
社会的差別や武力紛争などさまざまな困難に直面する人々とともにその背景や原因を考え、人間が人間らしく生きるための権利を取り戻すための支援を行います。
違いを認めあう共生社会を
実現します。
民族、宗教、政治的立場による分断を越えて相互理解を進めるために、市民レベルの交流を通して共生の社会づくりを推進します。
政策提言によって
社会を変革します。
人々が置かれた状況と背景にある問題について発信や提言を行い、問題の解決に取り組む市民ネットワークに積極的に参加し、ともに国際社会や日本社会に働きかけ解決への道につなげます。
私たちJVCは、アジア諸国で起こる戦争や難民の問題をニュースで見た市民による、「居ても立っても居られない」想いと行動から生まれました。JVCはボランティアを「無償の人材」ではなく、自発的につながり、支え合いたいという意志から「自発的に動く人」として捉えています。問題が生まれる構造をそのものを変えるためには、現地の人と共に活動し、社会が変わる仕組みを創っていく人が、この世界にたくさん必要です。支援のプロとしてではなく、まずは「市民」と「市民」として向き合う人々が集う「場」でありたい。そんな願いを、JVCは「ボランティアセンター」という名称に込めています。



JVCの取り組み
JVCは世界各地の困っている人々に、足りないものをあげるのではなく、つくる方法を一緒に考える。紛争で傷ついた人を助けるだけではなく、紛争を起こさない道をつくる。
「問題の根本にこだわる」。この思いを貫き活動しています。
代表メッセージ

JVC代表理事熊岡 路矢
2024年11月にJVCの理事に戻り、18年ぶりに代表理事となりました。2000年代から、世界、アジア、日本の政治、社会、経済も、またNGOを巡る環境も大きく変わりました。
2024年は、元日からの能登半島地震とその被害に大きな衝撃を受けました。「コロナ禍」の直前に、能登半島のごく一部ですが、輪島の朝市ふくめ町や農村を訪れた時のことをいまも思い出しています。
2025年1月現在、私たちJVCの海外活動地は、パレスチナ、スーダン、イエメン、ラオス、コリアと、政治状況の厳しいところばかりです。どの時代にも止められない戦争がありましたが、現在の「狂気」ともいえる戦争指導者の在り方は、異常です。
他方、日本でのある種の二季化(猛暑の夏が長期化し、春秋が短くなる傾向)ふくめ、気候変動・温暖化熱帯化の傾向が強まる一方です。JVCのOBOGや関係者の多くが有機農業に取り組み、「提携」(生産者⇔消費者)を実践するのも、食の安全・安心だけでなく、自然環境を守る意思を示していると思います。
現在、ある種の新しい「東西冷戦の時代」と言われていますが、本来の冷戦時代(1947~1991)のさなかの1980年に誕生したJVCも今年で45周年です。小さい団体として、若いスタッフを中心に、現実的に出来ることを淡々と続けていきたいと思っています。(2025年1月)